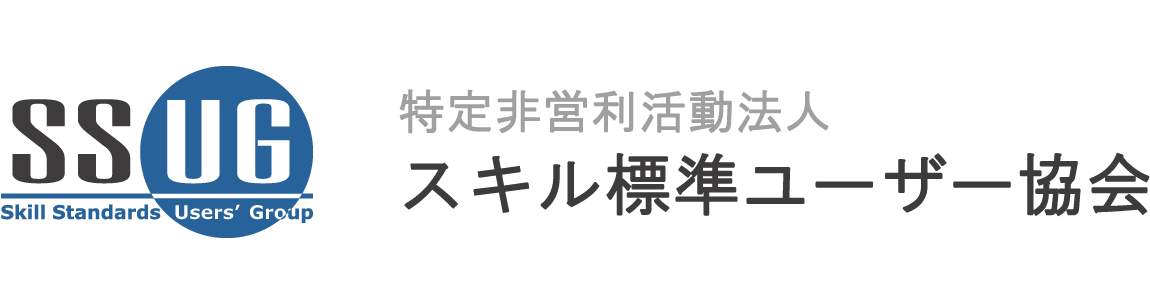●「現場とつながる、企業と学び合う」──スキル標準ユーザー協会・情報交流委員会のリアルな魅力
特定非営利活動法人 スキル標準ユーザー協会
スキル標準活用グループ 担当理事 松本 道典
人材育成やスキルの見える化の重要性が語られるようになって久しくなりました。
ITSSやiCD、DSS-Pといったスキル標準は、企業がこれらの取り組みを実現するための有効な手段として整備されてきました。
しかしながら、制度を作ることと、それを現場で"生かすこと"には大きな隔たりがあります。
担当者として、「どうすれば現場に定着するのか」「他社はどんな工夫をしているのか」を知りたくても、参考になる実践情報がなかなか手に入らない。
そんな課題意識から始まったのが、スキル標準ユーザー協会の「情報交流委員会」です。
2カ月に一度、全国から集まる"実務者の対話の場"
情報交流委員会は、2カ月に一度、原則対面形式で開催されており、首都圏をはじめ、大阪・名古屋・広島など地方開催も交えながら継続しています。
特徴的なのは、業種や企業規模を問わず、同じような課題意識を持つ参加者が集まり、非常にフラットな雰囲気で対話が交わされる点です。
導入状況や進捗は企業ごとに異なりますが、共通しているのは「人材を育てたい」「制度を"使える"ものにしたい」という思いです。
"うまくいかなかった話"が、最大の学びになる
情報交流委員会では、「成功事例」だけでなく、「試してみて失敗したこと」「その失敗から学んだこと」も積極的に共有されます。
たとえばある企業では、スキルの見える化を急ぎすぎて、細かく定義した結果、社員が使いこなせず制度が機能しなくなったという話がありました。
その後、対象役割(人材像)やタスク、スキル項目を絞り、現場のフィードバックを受けながら柔軟に改善していった過程が共有され、「自社もまさに同じ状況だった」「焦らず段階的に進めることの大切さに気づいた」という共感が広がりました。
このように、"うまくいかなかった経験"を率直に語れる空気があることこそが、情報交流委員会の魅力です。
共通言語だからこそ、議論が深まる
参加企業の多くは、ITSSやiCD、DSS-Pなど、スキル標準を導入・活用しています。
この"共通言語"があることで、たとえば「評価制度とスキル定義の関係」「定義の粒度調整」といった実務的な話題も、具体的かつスムーズに共有されます。
制度の「使い方」や「見直し方」まで含めて話し合えるのが、この委員会の大きな価値です。
現場を見るからこそ得られる"納得感"──年1回の企業訪問
情報交流委員会の中でも特に参加者からの評価が高いのが、年に一度の企業訪問企画です。
これは、実際に企業の現場を訪ね、制度運用の"実物"を目にし、担当者の生の声を聞くことができる特別回です。
昨年は北海道・余市のニッカウヰスキー余市蒸留所を訪れ、製造現場の人材育成や技能継承の工夫、現場との信頼構築の工夫などを体感しました。
単に制度だけでなく、組織文化や職場の空気感に触れたことで、参加者の理解がぐっと深まりました。
今年は、キリンビールの工場見学を予定しています。
製造業における人づくりの現場を間近に見ながら、スキルマネジメントの"実践の知"を得られる機会として、すでに多くの参加希望が寄せられています。
初めてでも大丈夫。"聞くだけ参加"も歓迎します
「自社ではまだ制度が整っていない」「知識に自信がない」という方もご安心ください。
情報交流委員会は、経験の有無にかかわらず、誰でも参加できる開かれた場です。
最初は聞くだけでも構いません。
他社の話を聞いているうちに、自社との違いが見えてきたり、次に何をすべきかのヒントが得られたりするはずです。
最後に──制度は"現場で使われてこそ意味がある"
私たちは、制度や仕組みを"導入すること"そのものがゴールになってしまうことに、常に注意を払っています。
本当に重要なのは、「制度が現場でどう使われ、どう育てられていくか」というプロセスです。
各社の歴史、経営戦略、人材育成方針を踏まえた取り組みは、業界・業種・規模が違いを超えて、自社にとっても大いに参考になることです。
情報交流委員会は、その「設計コンセプト」や「使い方の知恵」、「育て方の工夫」を、実際に取り組んでいる企業同士で共有し合える貴重な場です。
これから制度の導入を検討している方、いま改善に取り組んでいる方も、ぜひ一度この委員会にご参加ください。
現場に根ざした、リアルで実践的な学びが得られるはずです。